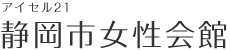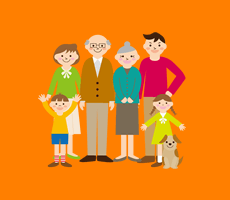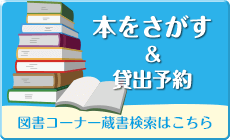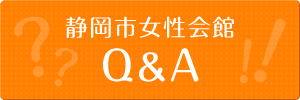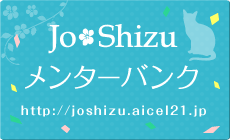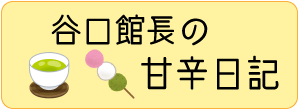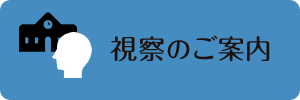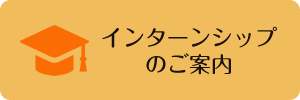災害時の被害を最小限に抑える「減災」という言葉はだいぶ浸透してきました。でも「男女共同参画とどんな関係が?」と思った方もいらっしゃるでしょう。16日開催の防災講座で、講師の池田恵子静岡大学教授が、そのわけを明快に解説してくれました。
池田先生は東日本大震災後、被災地への支援活動に女性の視点を取り入れるための調査、研究を行い、2014年4月からは「減災と男女共同参画研修推進センター」共同代表を務め、全国を飛び回っていらっしゃいます。
「同じ支援で皆平等では被害が拡大する」と池田先生は指摘します。なぜなら、性別・立場別で直面する困難に違いがあるから。避難所生活で、女性や乳幼児、障害のある人にとっては、「着替えや授乳ができない、洗濯物が干せない」などの困難が生じました。物資面では、女性用品・下着、乳幼児用・介護用品の不足に加えて、「男性のみによる配布」もハードルになりました。
支援物資に対する要望調査でも、男女別にみると「生理用品」「粉ミルク」「小児用おむつ」「おしりふき」などに大きな差が出ていました。DV、性暴力の発生など安全の問題も、男性と女性では困難が異なります。ライフラインが復旧しない中で、女性は家事、家族の世話、炊き出しの負担(無償労働)が増え、労働分野では女性が先に解雇され、失業率が増加するなどの差別も顕在化しました。
調査から分かってきた実態をどのように減災につなげるか。人々の〈違い〉に配慮した体制・支援をどのように実現するか。この続きは次回へ…。

「多様な視点で地域の防災力アップ」講座の一場面